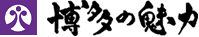博多の豆知識
豆知識 博多の地層~開発の歴史~
福岡市博物館の博多にまつわる豆知識をご紹介します。 博多エリアはその昔、海に突き出た砂丘でした。 日本有数の港町として発展する.........
豆知識 外国語でまち歩き~ぶらぶら福岡~
歴史や生活の日本文化を体験しながら散歩を楽しんでもらえるウォーキングイベントコースを、外国語の通訳付きでご案内します(日本人の方には、日本語.........
伝統文化 くぐると無病息災の御利益!?博多どんたくの傘鉾
博多どんたくの三福神の行列で見かける華やかな傘鉾(かさぼこ)。 さまざまな絵や書が描かれた傘鉾は三福神(福神,大黒,恵比須)の各行列にありま.........
豆知識 どんたくとは語源はオランダ語
博多どんたくのどんたくの語源は、オランダ語の「ゾンターク」で日曜日や休日という意味です。 明治のはじめ頃から用いられているようで、平成生まれ.........
豆知識 博多の秋の賑わい博多秋博
博多では、春の「博多どんたく」、夏の「博多祇園山笠」と伝統ある祭りが有名ですが、秋にも博多らしいイベントがたくさん開催されています。 博多で.........
豆知識 博多弁を少しご紹介します
1.「いぼる」は「はまる、埋まる」こと ぬかるみに足を取られた時などに使います。 2.「えずい」は「こわい、ひびる」こと 怖がりの人のことを.........
豆知識 博多を学ぶ!?博多っ子講座
博多のまちおこし団体「はかた部ランド協議会」が開催する、博多の歴史や文化など幅広~い分野を学ぶ「博多っ子講座」。 1年間に8回(月1回)開催.........
伝統文化 山笠のあるけん博多たい!
「山笠のあるけん博多たい!」 多くの人が知っているこの有名なフレーズ。 元々は「洋菓子の欧州」という会社が販売していた『伝統名菓 博多山笠』.........
伝統文化 博多仁和加(はかたにわか)ユーモアな即興笑劇
博多仁和加は、福岡市指定無形民俗文化財として、長い歴史と伝統を持つ郷土芸能です。 「ぼてかずら」に「にわか面」と言われる半面を着け、博多弁を.........
食文化 うどん・そばも饅頭も発祥の地博多
うどんといえば讃岐、そばは信州などが有名ですが、うどんもそばもそして饅頭も博多が発祥の地と言われているのですよ。 鎌倉時代の高僧である聖一国.........