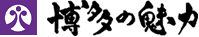博多の豆知識
豆知識 博多の地層~開発の歴史~
福岡市博物館の博多にまつわる豆知識をご紹介します。 博多エリアはその昔、海に突き出た砂丘でした。 日本有数の港町として発展する.........
豆知識 外国語でまち歩き~ぶらぶら福岡~
歴史や生活の日本文化を体験しながら散歩を楽しんでもらえるウォーキングイベントコースを、外国語の通訳付きでご案内します(日本人の方には、日本語.........
豆知識 どんたくとは語源はオランダ語
博多どんたくのどんたくの語源は、オランダ語の「ゾンターク」で日曜日や休日という意味です。 明治のはじめ頃から用いられているようで、平成生まれ.........
豆知識 博多の秋の賑わい博多秋博
博多では、春の「博多どんたく」、夏の「博多祇園山笠」と伝統ある祭りが有名ですが、秋にも博多らしいイベントがたくさん開催されています。 博多で.........
豆知識 博多弁を少しご紹介します
1.「いぼる」は「はまる、埋まる」こと ぬかるみに足を取られた時などに使います。 2.「えずい」は「こわい、ひびる」こと 怖がりの人のことを.........
豆知識 博多を学ぶ!?博多っ子講座
博多のまちおこし団体「はかた部ランド協議会」が開催する、博多の歴史や文化など幅広~い分野を学ぶ「博多っ子講座」。 1年間に8回(月1回)開催.........
豆知識 しゃもじどんたくしゃもじの起源
どんたくに参加される多くの方がしゃもじを持って舞台やパレードに参加し、しゃもじを打ち鳴らしながら踊られます。 その起源となったとされる一説は.........
豆知識 東京タワーの弟!?博多ポートタワー
市内が一望できる博多港のシンボル「博多ポートタワー」を設計した,建築家・内藤多仲氏は,東京タワーや大阪の通天閣なども手がけており,彼が戦後に.........
豆知識 博多のアイデアマン 田中諭吉
節分の時期になると,櫛田神社の入口に飾られる「大おたふく面」 これは,博多のユニークなアイデアマン田中諭吉さんが.........
豆知識 ホワイトデー 起源は博多に
今やすっかり定着しました3月14日のホワイトデーですが、その始まりには諸説があります。 全国飴菓子工業協同組合や東京の不二家の元祖節もあるよ.........