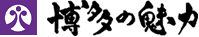福岡市博多区の南端に「雑餉隈」という難読の所が在る。この地名は読を何と読むのか、他所から来た人によく聞かれる。「ざっしょのくま」と読むが、この地名の由来について、江戸時代の黒田藩の学者貝原益軒の編になる地誌「筑前国続風土記」にはこう記されている。
『御笠森の西にあり。宰府へゆく大路に町あり。此町兩郡二村にかゝれり。東側は當郡(御笠郡)山田村に属す。西側は那珂郡井相田村に属せり。此所宰府参詣の人の足を休むる所にて、酒食を品々あきなふ肆(いちくら)ある故、雑餉隈と名付けるにや。又むかし太宰府官人の雑掌居たりし所なるか、いぶかし。』『太宰府へ参詣する官道に在って、途中休憩し、食事や飲酒などして一休みしていた。食事を出す店や宿などがあったことから雑餉隈と名前が付けられた。また、昔太宰府政庁の雑務に従事した役人が居たとのいわれがある。』との内容。(「隈」は隅っこに所在したという意味)雑餉隈は、むかし「間の宿(あいのしゅく)」と呼ばれていた。現在の大野城市雑餉隈町界隈であろう。また、JR南福岡駅周辺に三郡(那珂郡、席田郡、御笠郡)の郡役所があったとのことである。近くに在る『桜並木』は見頃の時期は美しい。