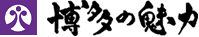隻流館(せきりゅうかん)は1652年に流祖二神半之助正聴(ふたがみはんのすけまさあき)が興した双水執流(そうすいしりゅう)の伝統を受け継ぐ由緒ある道場です。福岡藩の柔術指南役でもありました。玄関に掲げられた扁額の「隻流館」は、第13代黒田長成公の揮毫で桜谷の号があります。
双水執流は、柔術(組打(くみうち))と居合術(腰之廻(こしのまわり))からなる総合武術で臨機応変に身体を自由自在に働かせ人生を意義あるものにすることを目指して継承されています。前館長の16代舌間萬三宗利(したままんぞうむねとし)氏は、2005年に福岡市無形文化財保持者に認定されました。道場の正面には鹿嶋神宮と香取神宮が祀られ、嘉納治五郎(かのうじごろう)揮毫の「柔能制剛」と「身心自在」の扁額が掲げられています。
また千本取は、厳しい修業法の一つです。1868年に第12代舌間慎吾宗継(したましんごむねつぐ)氏が考案、 1人の試練者が50人を超える寄せ子の一団と約8時間かけて千本の乱取りに挑みます。投げても投げられても一本とするそうです。平和台を作った岡部平太も千本取を成し遂げました。達成者の名札が道場壁に掛けられています。道場の生徒は、日本人だけでなく海外の方も在籍しています。支部の双水執流柔術会はニューヨークとオーストラリアにあるそうです。
ところで、現在の隻流館の入り口には「旧金屋小路」の石碑があります。太閤町割りの七小路の一つ、ここには明治初期に博多発の本格的劇場「教楽社」が開場しました。大正時代になると近くに最新の設備とサービスを備えた「大博劇場」も開場し、御供所は博多芝居の中心になり黄金時代を支えます。双水執流略歴によりますと隻流館道場は福岡城内、西中洲、魚町、瓦町などを経て1896年現在地へ。芝居小屋(開明舎)を道場に改築しました。当時の名残があります。その後、建て替えても寄席の形を残し続けているそうです。
古くからの地域と共存しながら伝統を受け継ぐ双水執流隻流館、魅力ある道場でした。