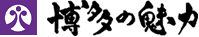中呉服町に『旧上金屋町』の博多旧町名石碑が建っています。昔は釜師(釜などを鋳造する職人)が多く住んでいたので金屋町と名付けられたそうです。碑文には『この町に鋳物師山鹿五兵衛が居住していたので金屋町上と言えり』とあります。
山鹿氏は18世紀中頃活躍した筑前芦屋の山鹿出身の釜師。旧金屋町での鋳造品の現存例は戦時下の金属供出のため非常に少ないのですが、この山鹿氏の作品である喚鐘が福岡市西区の今宿にある栄昌寺にあります。栄昌寺は歴史ある浄土宗のお寺でかつては博多区の上川端にありました。福岡大空襲の被害、再建を経て、2002年に現在の地に移転されています。
市の有形文化財でもあるその喚鐘は1769年にお寺のご先祖様が山鹿五兵衛の芦屋釜に依頼して鋳造されたものです。戦争中金属供出の要請を受け、一度は八幡製鉄所へ送られます。その後お寺は福岡大空襲で大変な被害を受けてしまいますが奇しくも喚鐘は溶解寸前、終戦となります。その後たまたま別のお寺の方が購入され、使用されていましたが近年になって譲渡を受けることとなり、栄昌寺が現在の地への移転する際にあらためて寄進されたそうです。
喚鐘は現在もお寺で現役で使われ、高く美しい音色で時を告げています。境内には福岡大空襲の犠牲者を悼む『じゅうご地蔵』もあり、250年以上も前に博多の旧金屋町で鋳造された喚鐘が失われることなく今に至っている経緯を思うととても感慨深いものがありました。