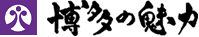7月の博多祇園山笠がおわると夏本番。そして、8月には夏のお祭りが多く行われています。その中の多くは、今から約290年前の享保期(1716~36)徳川八代将軍吉宗の治政中に勃発した、特に西日本に甚大な被害をもたらした「享保の大飢饉」によるものです。
当時博多においては6千人(人口の約3分の1)が死亡したと伝えられており、その惨状を物語っています。今では博多部には、その供養祭が行われる各所やお堂に吊るされた灯籠が暮れ時の空にぼんやりと灯り、古の歴史を感じさせます。
今夏は、その内の一つ御笠川沿いの飢人地蔵尊の大施餓鬼法要に参ってきました。今回はお祀りを受け継いでいる旧町(西門と旧中小路)の方に情緒たっぷりとお話を聞くことができました。
当時の自然災害とウンカの大発生で大飢饉に苦しんだ多くの農民たちが、今日の明日の食糧を求めて福岡城下をめがけ流れて来たそうです。博多では旧西町浜(現奈良屋町辺り)や魚町浜に粥所が設置されたそうですが、残念ながらそこへたどり着く前に行き倒れ亡くなった方も数多くいたそうです。
そして、後の人たちがその場所に石の地蔵尊を一基建て、聖福寺の依託により祭祀を行ってきました。8月24日には聖福寺全山住職による施餓鬼会の回向が執り行われています。お堂の近くには都市高速千代口があり、通常まさに都会の喧騒の中にありますが、午後7時頃から法要が始まると、ご住職方の読経が堂内で響き渡り、自然と先人への思いへと導いてくれたように感じました。
お世話人のお話の中で「近辺には“飢人地蔵尊“と銘がある碑がある場所が多いのは、その被害の甚大さを物語っています。ぜひ先人たちを弔ってやって下さい」という言葉で、一層想いを深めました。
また、同日には中洲博多川沿いで川端飢人地蔵尊・夏大祭があり、最終日24日の午後8時から灯籠流しが行われました。この供養は上川端通地蔵組合の皆さんにより続けてこられ、奉じる線香の煙が絶えないほど地域に密着した供養祭です。